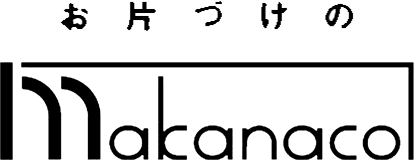INFORMATION
つい詰め込みがちな引き出し…“使いやすさ”が劇的に変わる見直し術
本来の自分の力を活かして無理せずらくに♡家庭円満をサポートするブログ担当の松下さおりです。
makanacoのブログに遊びに来ていただき誠にありがとうございます☺️
先週京都の実家に帰っていてブログお休みして
おりました。なので今週は今日と明日書きますね。
ちょうど秋の味覚の季節
栗ご飯おいしかった♡
10月はキッチンについて書いております。
2回目はキッチンの引き出し。
気づけば“なんでも入れ”になっていませんか?
割り箸、輪ゴム、使いかけのラップ、なぜか増えるスプーン…。
毎日使う場所だからこそ、少しずつモノが増えていきます。
でも本当は、ちょっとの工夫で驚くほど使いやすくなる場所なんです。
まずは「全部出す」より“1段だけ整える”
「全部出して仕分けましょう!」と言われると、それだけで気が重くなりますよね。
だから今日は、“1段だけ整える”でOK。
たとえばカトラリーの引き出し。
・よく使うスプーン・フォーク
・めったに使わないアイススプーン
・子どもが使わなくなった小さな箸
一緒に入っているだけで、毎回探す手間が増えています。
まずは「毎日使うものだけ」にフォーカスして並べ替えましょう。
ポイントは「取り出す動きの少なさ」
プロが意識しているのは、
“見た目”より“動作”。
片づくキッチンは、1つのモノを取るときにどれだけ動かすかで決まります。
・フタを開ける
・重ねた上のモノをどける
・引き出しを2段開ける
この「ちょっとした動作」が積み重なると、いつの間にか面倒になってしまうんです。
だからこそ、よく使うモノほどワンアクションで取れる位置に置くのが理想。
「すぐ取れる=片づけもすぐ戻せる」
これが“使いやすさ”の正体です。
見直すだけで時短になる!わが家の事例
以前、あるお客様のお宅でこんなことがありました。
毎朝バタバタして、子どもに「ママ、お箸どこ?」と聞かれるたびにイライラしてしまう…。
でも実は、箸が“シンクの真下”に入っていたんです。
朝の動線を考えて、レンジ横の一番上の引き出しに移動。
たったそれだけで、朝の「探す」「聞く」「イラッとする」がなくなりました。
片づけって、思いやりの形でもあるんです。
自分も家族もストレスなく動ける仕組みは、暮らし全体を穏やかにしてくれます。
それでも片づけきれないときは
「使いやすくしたいけど、何をどこに置けばいいか分からない」
そんな方が本当に多いです。
プロの片づけは、“見た目を整える”ことよりも、
その家の暮らし方に合わせた仕組みを作ること。
だから一度整うと、リバウンドしにくくなります。
自分では気づけなかった“家事の動線”が見えると、
「こんなにラクになるんだ!」と驚かれる方がほとんどです。
3回目は、「片づけてもすぐリバウンドする原因」を心の視点から見ていきます。
モノではなく、“気持ち”が片づけを止めている理由を知ると、
キッチンがぐっと優しい空間に変わりますよ。